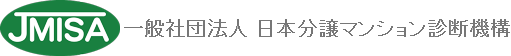このコーナーでは、標準管理規約や標準管理委託契約の改正内容について、何故改正したのか説明してきましたが、外部管理者をどう捉えるかについては特に追加・改正項目等はなく、巻末コメントに指針のみが記載されています。
今回はそれについて考えたいと思います。
****************************************
◎理事長や理事への成り手がいないので、適当な外部の方に任せられないのかな?
****************************************
【マンション標準管理規約(単棟型)コメント:抜粋】
(全般関係)
~中略~
③近年、マンションの高経年化の進行等による管理の困難化やマンションの高層化・大規模化等による管理の高度化・複雑化が進んでおり、これらの課題への対応の一つとして、外部の専門家の活用が考えられる。
~中略~
外部の専門家が管理組合の運営に携わる際の基本的なパターンとしては、(~中略~)
(1)従来どおり理事会を設け、理事会役員に外部専門家を選任するパターン
(2)外部専門家を区分所有法上の管理者として選任し、理事会は監事的立場となり外部管理者を監視するパターン
(3)外部専門家を区分所有法上の管理者として選任し、理事会は設けないパターン
の三つが想定される。
~中略~
なお、近年、既存マンションにおいて、役員の担い手不足等を背景としてマンション管理業者が管理者として選任される事例や、新築マンションにおいて、マンション管理業者が管理者に就任することを前提に分譲される事例が増加してきているが、この標準管理規約では、このような場合における管理方式は想定していない。(~中略~)
【さらに別添として、上記(1)~(3)のパターンで想定されるケース(マンションの特性)が以下のように記されています。】
(1)従来どおり理事会を設け、理事会役員に外部専門家を選任するパターン
・運営面の不全の改善
・計画的な大規模修繕等の適切な実施、耐震改修・建替え等の耐震対策等専門的知見が必要な場合を想定
*限定的な専門性が求められるケースも多くある。
(2)外部専門家を区分所有法上の管理者として選任し、理事会は監事的立場となり外部管理者を監視するパターン
・高い専門性と透明性、区分所有者の利益の保護や最大化のニーズの高いマンション(大規模な新築マンションなどを中心に想定)
*総会は意思決定機関、管理者は知見豊富な執行者、理事会は監視機関、と分担や責任の明確化が期待できる。
*さらに、専門性が高く、時間的な拘束が強く心理的な負担も大きい管理費回収訴訟、反社会的勢力、被災対応等の特定問題も担当することも想定。
(3)外部専門家を区分所有法上の管理者として選任し、理事会は設けないパターン
・高い専門性と透明性、区分所有者の利益の保護や最大化のニーズが高いが、規模の小さいマンション
・理事長の成り手がいない例外的なケース
*支援的性格が強いケース
****************************************
以上のとおり、一口に外部管理者といっても、管理組合の形式やその中での外部管理者の位置づけ・使命等をどう取り纏めていくかについては、マンション毎の個別事情に鑑みた検討が必要なことがご理解頂けるかと思います。
また昨今、「役員の成り手不足に対応した管理業者管理方式」に変更するケースも見受けられます(上記(3)の展開型とお考え下さい。)。
この場合には、例えば管理会社が大規模修繕工事等を元請しようとする際、管理組合側の意思決定も当該管理会社に委ねられる、といった複雑な状況(利益相反)に出くわさないとも限りません。
当機構のマンション管理士は、外部管理者の必要有無・必要な場合の選定手法や管理組合形式の見直し有無・それに付随する管理規約改正や総会決議の進め方等について難しい言葉を使わずにアドバイスできるものと思います。
お気軽に声がけ下さい。
さいとうたけろうマンション管理士事務所
齋藤太桂朗